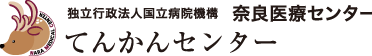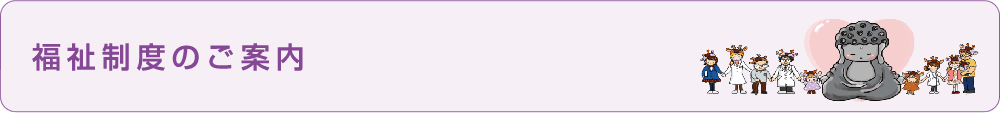
てんかんは、日本では精神保健福祉法に基づき法的に支援することが位置づけられています。また、公費負担制度とは別に医療保険の制度税金の医療費控除などのさまざまな助成制度があります。
自立支援医療費制度
【対象者】
てんかんと診断された人
【対象となる医療費】
指定された医療機関(原則1カ所)の外来受診のみで利用可能。保険適用されている外来でのてんかんに関わる診断、検査、薬などの医療費が原則1割となります。
【申請方法】
所定の申請書と診断書及びマイナンバーの分かるもの又は保険証の写し(同じ医療保険加入者全員分)、課税証明書など所得が確認できる書類を、住んで いる市町村窓口に提出します。
【有効期限】
1年間。引き続き利用する場合は更新手続きが必要です。
【利用者負担】
原則1割。ただし、世帯の市町村民税の課税額や病状等に応じて窓口での支払いに上限額があります。
1か月の医療費上限額
| 世帯所得 | 上限額 | |
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 | |
| 市町村民税
非課税世帯 |
受給者の収入が80万円以下 | 2,500円 |
| 受給者の収入が80万円以上 | 5,000円 | |
| 市町村民税 課税世帯 |
市町村民税 33,000円未満 | 5,000円 |
| 市町村民税 33,000円以上235,000円未満 | 10,000円 | |
| 市町村民税235,000円以上 | 20,000円 | |
精神障害者保健福祉手帳
てんかんの場合は、次に示す①から④の発作の頻度を基準に等級が決められています。
① 意識障害が起き、状況にそぐわない行動を示す発作。
② 意識障害の有無にかかわらず転倒してしまう発作が月に1回以上現れ、常時介護が必要な場合。
③ ぼーっとしてじっと動かなくなってしまい、意識を失ってしまうが倒れない発作。
④ 意識ははっきりしているが、意図した動きができない発作。
精神障害者保険福祉手帳の等級判定
| 級 | 内容 |
|---|---|
| 1級 | 上記で述べた①と②の発作が月に1回以上現れ、常時介護が必要な場合。(日常生活を一人で送ることができない) |
| 2級 | 上記の①または②の発作が年2回以上起こる場合。③または④の発作が月に1回以上現れる場合。(日常生活を送る上で援助が必要) |
| 3級 | 上記の①または②の発作が年2回未満起こる場合。③または④の発作が月に1回未満起こる場合。(日常生活や仕事など社会生活に制限を受けている場合) |
【申請方法】
市町村の担当窓口
【有効期限】
2年(引き続き利用する場合は更新手続きが必要)
【申請に必要なもの】
申請書・診断書または精神障害による障害年金を受給している場合その写し・本人の写真・同意書・障害基礎(厚生・共済)年金
【対象者】
定められた条件を満たしている人
【申請窓口】
市町村(基礎年金)
年金事務所・年金相談センター(厚生年金・共済年金)
【申請時期】
① 障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月後)に請求
② 障害認定日時点では症状が軽度で請求対象にならず、その後症状が悪化して障害状態になったときに請求(事後重症)
65歳の前々日までに請求が必要
精神障害者福祉手帳を持っていると受けられるサポート
●全国で受けられるサービスの例
- 税制上の優遇措置(所得税、住民税、相続税、自動車税などの減免、利子などの非課税
- NHK受信料の減免
- 携帯電話の基本料金の割引
- NTTの電話番号案内(104)が無料になる
- 生活保護の障害者加算の手続きが簡素化される
- 生活福祉資金の貸付
- 障害者職場適応訓練の実施 など
●都道府県、市町村独自のサービスの例
- 医療費助成
- 交通運賃割引
- 公共料金の割引
- 公共施設利用料の割引
- 福祉手当
- 公営住宅の優先入居 など
 |
いつでも、なんでも相談してください。 |
 |
日本てんかん協会へのお問い合わせ先 |
||